債務整理におすすめ弁護士・司法書士事務所12選|安い事務所はどこ?

借金を抱えて苦しんでいる人は少なくありません。金融庁や消費者庁がまとめた統計によると、2023年3月時点で3件以上の借入がある人は128万人、5件以上は12万人にのぼるといいます。
そんな苦しい状況から抜け出す道が、債務整理という選択肢です。債務整理は知識がないと自力ではなかなかできません。そのため、弁護士・司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。
今回は、債務整理におすすめな弁護士・司法書士事務所を厳選して紹介。「費用が安い」「ネット完結で相談がしたい」など目的に合ったおすすめの事務所もまとめています。

借金に困っている方、債務整理を検討している方はぜひご一読ください!

| 任意整理におすすめ | |
| 個人再生におすすめ | |
| 自己破産におすすめ |

涌井好文
就職氷河期の中、自身が非正規雇用を経験。それが労働者の雇用環境に興味をもつきっかけとなり、社会保険労務士の資格を取得。社会保険労務士として開業登録を行ってからは、企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活躍する。近年では活動の幅をウェブまで広げ、クラウドソーシングサイトやSNSを主軸に、記事の執筆や監修を行う。
| 本コンテンツで紹介している弁護士・司法書士事務所は、日本弁護士連合会の弁護士名簿または日本司法書士連合会に登録されています。そして、コンテンツ内で紹介しているサービスの一部もしくは全てに広告が含まれております。ただ、各コンテンツはランキング根拠に基づいて作成・紹介しており、広告が各サービスの評価に影響をもたらすことは一切ございません。詳しくは、モアマニのコンテンツポリシーと広告ポリシーをご確認ください。 |
【当サイトは金融庁の広告に関するガイドラインに則って運営しています】 |
目次
債務整理におすすめ弁護士・司法書士事務所12選
※債務整理におすすめの弁護士・司法書士事務所12選は全て未監修です。

弁護士・司法書士に依頼するのがおすすめな債務整理の方法は、任意整理・個人再生・自己破産の3つがあります。債務整理に強いおすすめの弁護士・司法書士事務所をぜひチェックしてみてください。
紹介している弁護士・司法書士事務所の評価および選定はランキング根拠に基づいて行っています。紹介している各事務所の基本情報は弁護士・司法書士事務所一覧をご覧ください。
はたの法務事務所

fa-check-square-o任意整理の着手金が0円!手持ちがなくても督促停止できる fa-check-square-o費用の分割払い可能!今お金が少ない人でも始められるるfa-check-square-o満足る満足fa-check-square-o満足度95.2%◎全国どこでも無料で出張 |
はたの法務事務所は、相談実績20万件以上を誇るほど人気の司法書士事務所です。司法書士歴27以上のベテラン司法書士が在籍していることからか、満足度は95.2%。
相談料・着手金・過払い金調査・全国への出張費は全て無料で、過払い報酬も12.8%〜と、比較的安い費用設定が魅力です。

また、手持ち資金が0円でも今月の支払いからストップさせ、督促を停止することができます。
相談者の「自宅や車は残して借金だけ減らしたい」「誰にも知られずに債務整理したい」といった希望にも沿い、解決への最善策を提案してくれるでしょう。

着手金が無料なので依頼しやすいですね。
| 着手金 /1件 | 0円 | 報酬金 /1件 | 22,000円〜 |
| 減額報酬 | 11% | 過払い 報酬 | 返還額の22%※ |
※10万円以下の場合:14%+計算費用11,000円。
※金額は全て税込み表示です。
| 所在地 | 〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階・6階(東京本店) |
| 対応 業務 | 債務整理、過払い金請求、相続・贈与関連、不動産・商業登記業務など |
弁護士法人・響

| fa-check-square-o問い合わせ・相談実績43万件以上! fa-check-square-o依頼前に費用を提示してくれる fa-check-square-o土日祝日を問わず365日24時間受付 fa-check-square-o100万円以下の借金でも対応 |
弁護士法人・響は、東京に2か所と大阪・福岡に事務所を構える弁護士事務所です。
多数の弁護士が在籍し、女性弁護士も複数名いるので、男性弁護士に話しにくい相談でも安心して依頼できます。電話やメールから法律相談の予約ができ、休日も24時間受付しています。
問い合わせと相談実績は43万件を超えと、実績ある事務所です。基本的に依頼者には1人の弁護士が担当しますが、依頼内容によっては事務所全体と連携・専門家と協議して、解決にあたってくれます。
弁護士法人・響は、必要な費用や追加費用がかかる可能性についても依頼前に説明してくれるため、費用の不安を持ったまま依頼をする必要はありません。
また、当サイトが行った独自のアンケートで、債務整理をした人が実際に依頼した弁護士・司法書士事務所を調査したところ、弁護士法人・響が1位を獲得しました。

| 弁護士法人 響 | 16.7% |
|---|---|
| サンク総合法律事務所 | 16.0% |
| はたの法務事務所 | 12.0% |
| ひばり法律事務所 | 7.3% |
| ベリーベスト法律事務所 | 6.7% |
| アディーレ法律事務所 | 6.7% |
| 東京ロータス法律事務所 | 3.3% |
| ウイズユー司法書士事務所 | 1.3% |
| 弁護士法人ユア・エース | 0.7% |
| アース法律事務所 | 0.7% |
| 司法書士法人 杉山事務所 | 0.0% |
| その他 | 18.7% |
アンケート調査:クラウドワークスにて実施
100万円以下の借金も引き受けているので、少額の場合でも気軽に相談できます。丁寧な対応と、費用の明確化を重視したい人におすすめの事務所です。

弁護士法人・響なら、初期費用は必要ありません。
| 着手金 | 55,000円〜 | 報酬金 | 11,000円〜 |
| 減額報酬 | 11% | 過払い 報酬 | 返還額の22%※ |
※訴訟の場合は27.5%。
※金額は全て税込み表示です。
| 所在地 | 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階(西新宿オフィス) |
| 対応 業務 | 債務整理、交通事故、労働問題、離婚相談、相続問題、刑事事件など |
出典:弁護士法人・響公式サイト
グリーン司法書士法人

相談料、着手金、減額報酬無料!無理のない分割払いも可能
任意整理の交渉実績は2万社以上!豊富なノウハウ
女性司法書士が在籍しており、同性に相談したい女性でも安心
必要に応じてファイナンシャルプランナーへの相談も可能
全国オンライン相談に対応!近くに相談できる事務所がない方におすすめ
グリーン司法書士法人の運営する東京大阪債務整理・自己破産相談センターは、大阪と東京に事務所を構えます。受付時間は、平日9:00~20:00、土日祝は10:00~17:00となっています。
借金問題に関する豊富な実績とノウハウが魅力。これまでの任意整理交渉実績が2万社を超える司法書士事務所です。
また、グリーン司法書士法人に依頼すれば、必要に応じて取り立ての即日ストップも可能です。
土日祝日を含めて、全国オンラインに対応しているので、忙しい方や事務所に足を運ぶのが難しい方にもおすすめします。

公式ホームページでは、今の借金がどのくらい減額できるのか、無料で診断を受けられます。気になる方は、まずこちらから試してみるとよいでしょう。
【任意整理する場合にかかる費用】
グリーン司法書士法人最大の特徴は、他社だと発生するケースの多い減額報酬が無料であることです。
| 着手金 | 0円 |
|---|---|
| 基本料金 | 21,780円(税込)~/1社 |
減額報酬 | なし |
過払い報酬 | 取り返した額の22%(税込) ※裁判での回収の場合28%(税込) |
経費 | 要問合せ |
| 所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目16−8 北斗ビル 3階 |
| 対応 業務 | 債務整理、相続問題、家族信託 |
出典:グリーン司法書士法人
サンク総合法律事務所

| fa-check-square-o取り立て・催促を最短即日でストップ fa-check-square-o初期費用0円!いまお金がなくても債務整理できる fa-check-square-o費用の分割払い・後払いOK! 月600件以上の相談実績 24時間365日受付/全国対応の借金専門相談窓口あり |
サンク総合法律事務所(旧樋口総合法律事務所)は、借金問題の解決実績が豊富で、問い合わせが月600件以上ある人気な弁護士事務所です。
人気の理由は、自分が納得いくまで何度でも無料相談ができ、借金に関する質問にわかりやすく答えてくれるから。新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえて、オンラインや電話での面談も24時間365日全国から受け付けています。
初期費用は0円(契約前まで一切料金がかかりません)かつ費用の分割払いが可能なので、現在手元に十分な資金が欠くても依頼が可能です。
また、家族や職場に知られにくいように配慮してくれたり、女性弁護士が在籍していたりと、誰でも気軽に相談できる環境が整っています。
最短即日で借金の取り立てや催促を止めてくれるので、今すぐ催促から解放されたい方にもおすすめです。

完済後の過払い金請求の着手金は、無料です。
| 着手金 /1件 | 55,000円〜※ | 報酬金 /1件 | 11,000円〜 |
| 減額報酬 | 11% | 過払い 報酬 | 回収額の22%※ |
※訴訟による場合は回収額の27.5%。
※金額は全て税込み表示です。
| 所在地 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-2-2 UUR京橋イーストビル2階 |
| 対応 業務 | 債務整理、貸金問題、離婚・相続・遺言、民事事件一般、不動産取引、刑事事件など |
ひばり(名村)法律事務所

| fa-check-square-o相談は何回でも無料! fa-check-square-o過払い金の着手金が0円 fa-check-square-o女性専用窓口が好評 fa-check-square-o東大法学部卒業・弁護士歴25年以上のベテラン弁護士が所属 fa-check-square-o家族に内緒で債務整理できる |
ひばり法律事務所は、事業拡大のために2020年7月に個人事務所(名村法律事務所)から、弁護士法人に組織変更した法律事務所です。
東大法学部を卒業した弁護士歴25年以上のベテラン弁護士が在籍しており、長年の経験にもとづき様々な相談に応じています。特に、債務整理やネットトラブルを得意とする事務所です。
また、女性弁護士も在籍しているので、女性に相談したいという人も安心して利用できます。
また、過払い請求の着手金は0円で、成功した場合のみ報酬を支払う仕組みです。
依頼にかかる費用が明確化されているため「弁護士に依頼すると高い」「いくら支払うかわからなくて怖い」という場合にも、不安なく依頼できるでしょう。

ひばり法律事務所なら、着手金の分割払いが可能です。
| 着手金 /1件 | 22,000円 | 報酬金 /1件 | 22,000円 |
| 減額報酬 | 11% | 過払い 報酬 | 返還額の22% |
| 経費 | 5,500円 |
※金額は全て税込み表示です。
| 所在地 | 〒130-0022 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階 |
| 対応 業務 | 債務整理、ネットトラブル、離婚相談、相続問題など |
ベリーベスト法律事務所

- 相談は何度でも無料!納得するまで話を聞いてもらえる
- 弁護士費用の後払いや分割に対応!※後払いは過払い金請求のみ
- 北海道から沖縄まで全国72か所に拠点
- 24時間365日問い合わせ受付
- 約350名在籍!ノウハウの豊富な弁護士に任せられる
ベリーベスト法律事務所は、全国72ヶ所※に拠点をおく規模の大きな法律事務所です。プライバシーに配慮したオフィスの個室以外にも、自宅や職場周辺など、相談する場所を選択できます。
※2023年10月現在
債務整理の相談中であることを周りに知られたくないという方のため、郵送物は真っ白な封筒でお送りするなどの対応が可能です。
約10年間で、債務整理の相談件数の累計は、36万件を突破しています※。またこれまでに回収した過払い金は、累計1,067億円を超えています。
契約前に見積もりを作成し、内訳まで丁寧に説明してもらえる上、分割払いも相談できるので、「弁護士に依頼したいけど費用面が心配」という方でも安心でしょう。

電話での受付は24時間365日対応、メールでの問い合わせも可能です。ただし時間帯によっては、相談予約のみの対応となる場合があるため、なるべく平日昼間の連絡がおすすめです。
※集計期間:2011年2月~2022年12月末まで
【任意整理する場合にかかる費用】
ベリーベスト法律事務所は、分割払いにも対応しています。(下記の任意整理依頼費用は、利息の支払いがなくなれば3年~5年で借金を完済できる見込みがある方の場合です。)※1
| 手数料 | 0円〜/1社〜※2 |
|---|---|
| 解決報酬金 | 22,000円(税込)/1件〜 |
成功報酬 | 取り戻した過払い金の22%(税込) ※裁判ありの場合:27.5%(税込) |
事務手数料 | 4万4,000円(税込)/1案件※3 |
※1費用が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変わっていた場合、 税法改正後の税率の消費税がかかることとなります。
※2 ※負債額に応じます。詳しくはお問合せください。
※2 時効援用が成立した場合、手数料の上限は55,000円(税込)となります。
※3 複数からの借り入れ含め借金相談1回の解決でかかる費用。金額は状況によって異なります。詳しくはお問合せください。
| 所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木1丁目8−7 MFPR六本木麻布台ビル 11階 |
| 対応 業務 | 債務整理、ネットトラブル、離婚相談、相続問題など |
出典:ベリーベスト法律事務所
東京ロータス法律事務所

| fa-check-square-o無料相談のしやすさが魅力 fa-arrow-circle-o-right何回でも・土日祝日でも・メール/電話でも・全国各地からでも相談OK! fa-check-square-o受任件数7,000件以上のノウハウを活かして法律問題を解決 fa-check-square-o和解後の返済も代行! fa-check-square-o分割払いもOK fa-check-square-o電話での問い合わせなら電話代無料 |
東京ロータス法律事務所は、借金問題や債務整理を得意とする弁護士法人事務所です。
受注件数は7,000件以上と多く、専門ノウハウを活かして借金問題を解決してくれるでしょう。

東京ロータス法律事務所が大切にしているのは、依頼者からじっくりとヒアリングし、一人一人に合わせた解決策を提案すること。
相談は何回でも無料で土日祝日も対応しているため、相談しやすいことがメリットです。
また電話での問い合わせも無料なので、問い合わせや相談にお金をかけたくない人におすすめできます。

相談費用は何度でも無料です。
| 着手金 /1件 | 22,000円 | 報酬金 /1件 | 22,000円 |
| 減額報酬 | 11% | 過払い 報酬 | 返還額の22%※ |
| その他 諸費用 | 5,500円 |
※訴訟の場合は27.5%。
※金額は全て税込み表示です。
| 所在地 | 〒110-0005 東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階 |
| 対応 業務 | 債務整理、借金問題、離婚相談、相続問題、不動産トラブル、刑事事件など |
ML司法書士事務所

| fa-check-square-o相談は何度でも無料! fa-check-square-o匿名OK!無料の借金減額診断あり WebやLINEから24時間相談受付 自分に合う最適な方法を提案してくれる |
ML司法書士事務所は、債務整理を中心に業務を行う法司法書士事務所です。江ノ島に近い神奈川県藤沢市を拠点としています。
専門的な用語や知識など、難しい内容があってもとにかく丁寧でわかりやすく説明してくれるのが特徴。長年の経験を生かして、個人の事情に配慮したヒアリングから自分に合った解決策を見出してくれます。
相談は何度でも無料で、WebやLINEからも相談を受け付けているので気軽に問い合わせが可能です。また、いくら借金が減らせるか無料でチェックできる借金減額診断の用意もあります。
相談は完全個室制となっており、プライバシーの観点からも安心して話ができます。着手するまでの費用はかからず、書類の用意もすべておまかせできるのは嬉しいですね。
気になる費用についても、任意整理における着手金の料金がほかの弁護士・司法書士事務所と比較して安く設定されています。

着手金の価格設定が比較的安い点は大きな魅力です。
| 着手金 /1件 | 11,000円〜 | 報酬金 /1件 | 11,000円〜 |
| 減額報酬 | 11% | 過払い 報酬 | 回収額の22%※ |
※訴訟による場合は回収額の27.5%。
※金額は全て税込み表示です。
| 所在地 | 〒251-0038 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡1丁目16番22号 |
| 対応 業務 | 債務整理 |
弁護士法人ユア・エース

| fa-check-square-o相談は何回でも無料! fa-check-square-o24時間受付でいつでも相談できる fa-check-square-o明確な料金プランと相談の流れで不安解消 fa-check-square-o依頼には専門チームで対応するので安心して任せられる |
弁護士法人ユア・エースは、債務整理や交通事故を中心に、さまざまな法律問題に対応している法律事務所です。
弁護士だけでなく医療顧問が付いているなど各専門知識を活かし、依頼には専門チームを作って対応します。専門チームを作ることで、迅速に対応し、早期の解決を目指しています。
依頼者の悩みに寄り添い、満足度を最優先にして成果を上げることを目標としているところが弁護士法人ユア・エースの魅力です。
初めて弁護士に相談する人の不安を理解し、解決までに依頼者にかかる精神的負担を減らせるように、コミュニケーションを密におこなっています。

弁護士法人ユア・エースも、費用が明瞭なので安心して依頼できます。
| 着手金 | 55,000円〜 | 報酬金 /1件 | 11,000円〜 |
| 減額報酬 | 11% | 過払い 報酬 | 返還額の22%※ |
※訴訟の場合は27.5%。
※金額は全て税込み表示です。
| 所在地 | 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階 |
| 対応 業務 | 債務整理、交通事故、消費者トラブル、離婚問題、医療事故、労働問題、相続問題など |
司法書士法人 赤瀬事務所

fa-check-square-o初回相談料が無料!借金の解決が得意 fa-check-square-o無料で借金をいくら減らせるかわかるるfa-check-square-o満足る満足fa-check-square-o土日・祝日・時間外でも対応してもらえる |
司法書士法人 赤瀬事務所は、大阪に拠点を構える司法書士事務所です。メディアでの紹介実績が豊富にあり、借金や相続、不動産登記などの相談を得意としています。
事前予約をすれば、土日・祝日でも対応可能。時間外でも柔軟に対応してもらえるところは、嬉しいポイントです。
また、無料で使える減額シミュレーションを利用すれば、たった3問で借金をいくら減らせるかわかります。
診断後は、相談までスムーズに進めますので「借金を解決したい」と本気で考えている方はぜひ利用してみてください。

報酬金は基本無料。分割払いに対応していますので、今お金がない方でも安心して相談できます!
| 着手金 /1件 | 22,500円(税込)~ | 報酬金 /1件 | 基本無料 |
| 減額報酬 | 11%〜 | 過払い 報酬 | 返還額の22% |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
| 対応 業務 | 債務整理、相続、不動産登記など |
アース法律事務所

| fa-check-square-o全国からの相談受付中!初回相談は無料 fa-check-square-o元裁判官の弁護士が相談に乗ってくれる fa-check-square-o事前予約で夜間や時間外も対応可能 fa-check-square-o3,500件以上の実績あり |
アース法律事務所は、全国から債務整理や借金問題の相談を受け付けている弁護士事務所です。元裁判官の弁護士が在籍しており、プロの目線からサポートしてくれます。
相談実績は3,500件超。債務整理や過払い金請求などの借金問題はもちろん、不動産関連や相続など取り扱い業務の幅広さが特徴です。
法律事務所の営業時間は平日の10〜19時ですが、電話やメールで事前に連絡すれば、時間調整のうえ土日祝日や夜間など時間外でも対応してくれます。
借金問題であれば初回の相談は無料。30分や1時間単位で費用が発生しないので、じっくりと相談ができます。
アース法律事務所は紹介者がいなくても相談できるので、気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

必要な弁護士費用をオープンにしてくれているので安心ですね。
| 着手金 /1件 | 22,000円 | 報酬金 /1件 | 22,000円 |
| 減額報酬 | 11%相当額 | 過払い 報酬 | – |
※金額は全て税込み表示です。
| 所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋2丁目12-5池伝ビル5階 |
| 対応 業務 | 債務整理、相続、詐欺被害、不動産問題など |
ウイズユー司法書士事務所

| fa-check-square-o家族に内緒で督促状をストップ! fa-check-square-o24時間・365日LINEや電話で相談可能 fa-check-square-o減額報酬なしだから低コストで借金を完済できる fa-check-square-o後払いや分割払いなど柔軟な支払い方法に対応 |
ウイズユー司法書士事務所は、闇金被害を含めた借金問題の解決に強い弁護士事務所です。LINEや電話、メールなどの方法で、24時間・365日いつでも相談できます。
減額報酬はかからず、幅広い支払い方法に対応しています。「できるだけ安く解決したい」や「すぐに弁護士費用を用意できない」といった方でも利用しやすいでしょう。
また、家族や職場にバレずに利用できるところもポイントです。「夫に内緒で借金を作ってしまった」といった状況でも、バレずに解決した事例が多数あります。

報酬金が1件あたり11,000円からと比較的リーズナブルな価格に設定されています。
| 着手金 | – | 報酬金 /1件 | 11,000円(税込)〜 |
| 減額報酬 | 無料 | 過払い 報酬 | 返還額の20% |
| 所在地 | 〒530-004 大阪府大阪市北区東天満2-9-1 若杉センタービル本館7階 |
| 対応 業務 | 債務整理、不動産登記、会社登記、未回収金など |
司法書士法人 杉山事務所

| fa-check-square-o毎月5億円以上!過払金請求の回収額が日本一! fa-check-square-o全国9事務所で無料相談を実施中 fa-check-square-o出張相談も無料だから地方でも利用しやすい fa-check-square-o大手消費者金融や信販会社の債務整理経験が豊富 |
司法書士法人 杉山事務所は、毎月10,000件以上の過払金や債務整理のお悩みを解決している司法書士事務所です。
大阪、東京、名古屋、福岡、広島、岡山、仙台、札幌と、全国9事務所で無料相談を実施中。年中無休で営業しているため、返済や督促などの不満をいつでも相談できます。
また、地方の方に向けて出張相談を無料で実施しているところもポイントです。全国各地の方が利用できます。借金問題をすぐに解決したい方は、ぜひ問い合わせてみてください。

着手金は0円!分割払いにも対応しています。
| 着手金 | 22,500円(税込)~ | 報酬金 /1件 | 27,500円(税込)〜 |
| 減額報酬 | 11%~ | 過払い 報酬 | 返還額の27.5%〜 |
| 所在地 | 【杉山事務所 大阪】 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波2-3-7 南海難波御堂筋ウエスト8F |
| 対応 業務 | 過払金請求、任意整理、自己破産、個人再生など |
出典:司法書士法人 杉山事務所
目的別!債務整理におすすめの弁護士・司法書士事務所
債務整理に強い弁護士・司法書士事務所は多数ありますが、それぞれにはきちんとした特徴があります。目的と特徴が一致した弁護士・司法書士事務所を選べば、スムーズに債務整理できるでしょう。
ここでは費用面や女性向けなどよくある目的に合わせて、債務整理におすすめの弁護士・司法書士事務所を紹介します。
| 費用が安い | はたの法務事務所fa-play-circle |
|---|---|
| 分割払いに対応 | サンク総合法律事務所fa-play-circle |
| 返済代行OK | 東京ロータス法律事務所fa-play-circle |
| 女性弁護士が在籍 | 弁護士法人・響fa-play-circle |
| ネット完結可能 | グリーン司法書士法人fa-play-circle |
費用が安い

費用が安い弁護士・司法書士事務所を探している方は、はたの法務事務所がおすすめ。はたの法務事務所では、以下の費用が全て無料になっています。
- 任意整理の着手金
- 相談料(回数問わず)
- 全国出張
- 過払い金調査
大きな強みは、任意整理の着手金が無料であること。他の弁護士・司法書士事務所では2〜5万円かかる着手金が、0円なのは非常にお得です!
| はたの法務事務所 | 無料 |
|---|---|
| ひばり法律事務所 | 22,000円(税込)〜 |
| 弁護士法人 響 | 55,000円(税込)〜 |
土日でも対応しているので、平日仕事などで時間が取れない場合でも利用しやすいメリットがあります。女性専用窓口も用意しており、相談しやすい環境づくりに努めています。
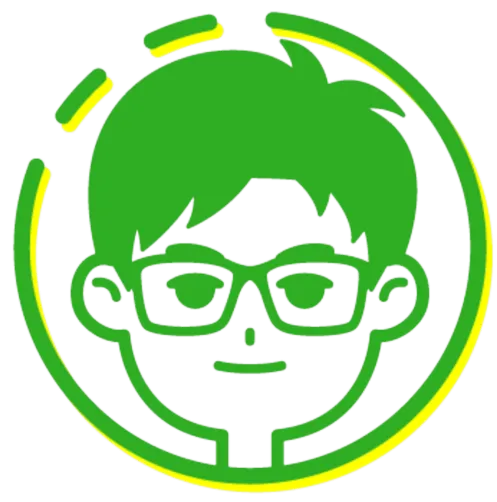
もちろん分割払いにも対応しています!
分割払いに対応

分割払いに対応している弁護士事務所を探しているなら、サンク総合法律事務所がおすすめ。分割払いだけでなく後払いにも対応しています。
そのため、まとまったお金がなくてもすぐに債務整理で借金を減額できます!
また、家族や知人に内緒で債務整理したい方にもおすすめ。サンク総合法律事務所はオンライン面談に対応しており、ネット完結で依頼まで可能です。
債務整理を正式に依頼すれば、借金の取り立てを即日でストップしてもらえます。返済の督促が多くて悩んでいるなら、相談してみてはいかがでしょうか。
返済代行をしてくれる

債務整理したあとに、債権者への返済がしづらい…という方は、返済代行に対応している事務所がおすすめ。東京ロータス法律事務所は、利用者のかわりに残りの借金を返済してくれます。
また、東京ロータス法律事務所は、受任件数が7,000件以上と実績も豊富。土日も対応しているので、平日になかなか時間が取れない方にもおすすめです。
いきなり事務所に行くのは勇気がいるかもしれませんが、東京ロータス法律事務所ならメールから無料で相談できます。費用の分割払いも対応しており、費用面で悩んでいる方も利用しやすいでしょう。
女性弁護士が在籍

「借金を抱えているけれど女性でも相談できるか不安」「女性弁護士なら安心して話せる」という方は、弁護士法人・響がおすすめです。
弁護士法人・響は複数の拠点に女性弁護士が在籍しています。公式サイトの弁護士紹介ページも作り込まれており、活動実績やコメントなどを確認できます。

どんな弁護士なのか把握してから相談・依頼できて安心ですね!
ネット完結可能

グリーン司法書士法人なら、事務所に出向かなくてもオンラインで相談できます。「事務所に行く時間がない」「かるく相談だけできたらいい」という方にぴったりです。
また、グリーン司法書士法人では、いま抱えている借金をどれくらい減額できるか無料で診断できるツールを用意。オンライン相談の前に、一度試してみてはいかがでしょうか?
債務整理におすすめな弁護士・司法書士事務所の選び方
ここからは、債務整理におすすめの弁護士・司法書士事務所の具体的な選び方について解説していきます。
選び方を参考にして、自分が納得できる弁護士・司法書士事務所に依頼しましょう。
費用が安い
借金で悩んでいるのに、弁護士や司法書士への依頼費用が高いと大変ですよね。そのため、費用が安いかどうかチェックするのは非常に重要でしょう。
日本弁護士連合会の調査によると、実際に債務整理を行った人の月収は、自己破産の場合10〜15万円が1位、個人再生の場合は30万円以上が1位でした。

個人再生した方でも平均的な月収の割合が高く、費用が安いところで債務整理するのが良いでしょう。

【自己破産の場合】
| 0〜5万円 | 13.23% |
|---|---|
| 5〜10万円 | 15.89% |
| 10〜15万円 | 23.06% |
| 15〜20万円 | 10.56% |
| 20〜25万円 | 13.79% |
| 25〜30万円 | 6.53% |
| 30万円以上 | 4.11% |
| 不明 | 2.82% |
【個人再生】
| 5万円未満 | 0.54% |
|---|---|
| 5〜10万円未満 | 1.07% |
| 10〜15万円未満 | 4.82% |
| 15〜20万円未満 | 17.67% |
| 20〜25万円未満 | 23.43% |
| 25〜30万円未満 | 23.29% |
| 30万円以上 | 27.31% |
| 不明 | 1.87% |
気になる弁護士・司法書士事務所があるなら、一般的な費用相場と比べて安いかどうかで選ぶのがおすすめです。ここで、一般的な弁護士・司法書士事務所の費用相場についてみていきましょう。
- 任意整理:1社あたり3万~5万円+成功報酬10%または2万円
- 個人再生:着手金22万円~33万円+成功報酬22万円~33万円
- 自己破産:着手金22万円~33万円+成功報酬22万円~33万円
上記の数字は目安ではありますが、相場より安い事務所なら検討してみることをおすすめします。
分割払い・後払いに対応
弁護士・司法書士に債務整理を依頼するとき、気になるのが費用ですよね。まとまったお金を用意するのが難しい時は、分割払い・後払いに対応している事務所がおすすめです。
分割払い・後払いに対応している事務所は、通常6回~12回程度に分割してくれることが多く、1年以内の返済となります。
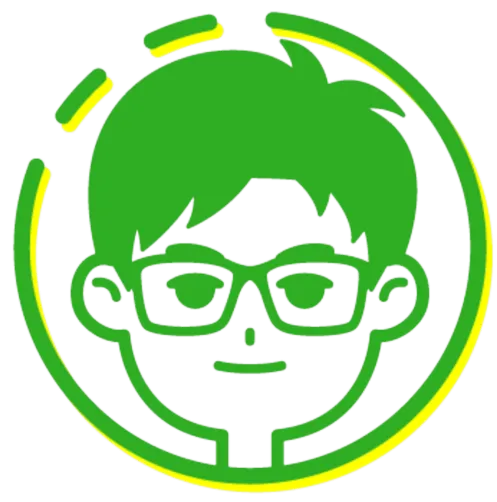
対応している場合、手元にまとまった資金がなくても依頼できます。
事務所によっては対応しているのにホームページや資料などに分割払い・後払いの記載がないこともあります。
その場合は、事務所に連絡して直接聞いてみることをおすすめします。
当サイトおすすめのサンク総合法律事務所なら、分割払い・後払いともに対応しているので、手持ちの資金がなくても依頼できます!
自宅からの距離
3つ目の選ぶポイントは、弁護士・司法書士事務所と自宅からの距離が近いかどうかです。
当サイトが実施した独自アンケート調査でも、債務整理を依頼した弁護士・司法書士事務所を選んだ決め手として、「自宅からの距離が近い」が1位にランクインしています。

| 自宅との距離が近い | 35.3% |
|---|---|
| 費用が安い | 30.0% |
口コミや評判が良い | 12.0% |
| 債務整理の実績が豊富 | 10.7% |
| メールやオンラインで相談できる | 9.3% |
| 土日祝日や夜間でも対応 | 1.3% |
| 分割払いや後払いができる | 0.0% |
| その他 | 1.3% |
アンケート調査:クラウドワークスにて実施
債務整理の無料相談は電話やメールといったオンライン上で完結できることが多いですが、最終的な委任契約や和解契約は事務所に行かなければいけません。
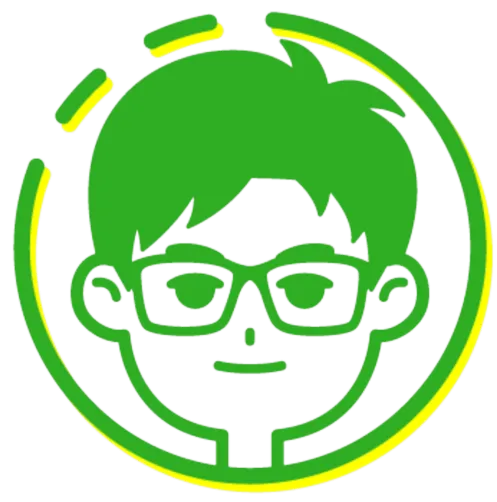
債務整理の内容にもよりますが、自己破産の場合は多くて4回以上事務所を訪問しなければならないこともあります。
オンライン会議アプリの「zoom」などを用いたWeb面談や出張相談などをしている事務所もあるため、近くにない場合は活用してみるとよいです。
また、依頼を進めていく中で自宅や勤務先などから事務所が近いと、すぐに訪問して対処することができるため、選ぶ基準として覚えておきましょう。
夜間・土日でも対応可能
弁護士・司法書士事務所を探すときは夜間・土日でも対応しているかどうか、確認しておくことをおすすめします。
理由は夜間・土日に連絡が取れる場合、スムーズに事が運びやすかったり、不安や疑問点をすぐに聞くことができるからです。

平日は仕事やパートなどで忙しく連絡が取りにくいという方は優先すべき選び方といえます。
また、メールや電話などの連絡を24時間365日対応しているかどうかも大きなポイントといえます。
すぐに連絡が取れる弁護士・司法書士事務所ほど解決するまでの時間が短くなりやすいので、なるべく時間をかけたくない方におすすめです。
債務整理の実績
弁護士・司法書士事務所を選ぶときに、重要となるのは債務整理の実績が明確な数字で表されているかです。
やはり、債務整理の解決件数や相談件数といった実績を前面にアピールしている事務所は、ほかの事務所よりも信頼度が高いといってよいでしょう。
| はたの法務事務所 | 相談実績20万件以上 |
|---|---|
| 東京ロータス法律事務所 | 受任件数7,000件以上 |
| 弁護士法人 響 | 相談実績19万件以上 |
また、依頼したい弁護士・司法書士事務所に債務整理を専門とする弁護士や、債務整理の知識に長けている司法書士が在籍しているかも確認するのがおすすめです。
口コミや評判
6つ目の選び方は、依頼を考えている弁護士・司法書士事務所の口コミや評判を参考にすることです。
特に債務整理関連の依頼に対しての口コミや評判は参考になるものが多く、人によっては解決までの時間や対応の早さなどを記載していることもあります。
Googleマップで口コミ・評判がよかった弁護士・司法書士事務所は以下の通りです。
| グリーン司法書士法人 東京オフィス | ★4.5 |
|---|---|
| ベリーベスト法務事務所 東京オフィス | ★3.8 |
| 弁護士法人 響 西新宿オフィス | ★3.2 |

ただし、口コミを信じすぎるのも良くなく、参考程度にとどめておき全体的な評価の高さで選びましょう。
口コミを確認するときは、利用者の目線からその事務所がどのようなところが良く、どのようなところが悪いのかを見るとよいです。
内容次第では、依頼を控えたほうが良い場合もあるため、選ぶときは必ず参考にしましょう。
【弁護士/司法書士に聞く】債務整理おすすめの弁護士・司法書士事務所の選び方
いざ債務整理の相談をしようと思っても、繊細な問題だけに躊躇してしまうものです。そこで当サイトの監修者である安井孟さん、佐藤一清さんに債務整理に関する独自インタビューを実施しました。
債務整理を検討している方や、弁護士・司法書士事務所選びで悩んでいる方は、ぜひとも専門家の意見を参考にしてみてください。
安井孟さんにインタビュー

安井孟
1993年3月28日生
中央大学法学部卒業
中央大学法科大学院終了
司法修習(前橋修習)
岸町法律事務所にて勤務
セントラルサポート法律事務所設立
Q:債務整理を依頼する弁護士・司法書士事務所の選び方について教えてください
債務整理を依頼する弁護士・司法書士事務所を選ぶ際には、次の3つのポイントから選ぶと良いでしょう。
- 費用
- 結果・実績
- 対応の良さ
費用
債務整理を依頼される際には、金銭的な余裕がなくて依頼しますので、当然費用は重要です。
そして、費用で選ぶと言っても、見た目の費用の安さだけで選ぶとかえって高額な費用であることも多々あります。具体的には、●万円~といったような費用設定を記載している弁護士・司法書士事務所もありますが、この場合には、実際に費用がいくらになるのか事前に確認することが大切です。
結果・実績
債務整理の場合、依頼する弁護士・司法書士事務所によって結果や実績は異なります。
任意整理で言えば、月々の返済額や利息の減免結果が依頼する弁護士・司法書士によって異なりますし、個人再生や自己破産で言えばスムーズに認可・免責が認められるか否かが異なります。
これらの結果や実績は、実際に依頼する弁護士・司法書士の方と面談を行う際に、見通しを聞くと分かりやすいでしょう。実績がある弁護士・司法書士であれば、見通しを的確に回答できる一方、実績がない弁護士・司法書士の場合、見通しがあいまいになることがあります。
対応の良さ
債務整理は、任意整理でも半年程度、個人再生や自己破産では1年程度は期間がかかります。
このように、依頼する弁護士・司法書士事務所との関係も長く続きますので、弁護士・司法書士事務所の方の対応が悪いと、非常にストレスになります。
そのため、依頼する弁護士・司法書士事務所を選ぶ際には、弁護士・司法書士や事務員の方の対応が良いこと(やり取りをしていてストレスにならないこと)も重要なポイントです。
Q:債務整理をする際の注意点について教えてください
債務整理をする際の注意点としては、依頼する弁護士・司法書士に自らの借入状況や収支状況を正確に伝えることです。
借入状況(借入金額、借入期間、保証人の有無等)は、弁護士・司法書士に依頼後、債権調査がなされますのでその際に判明しますが、仮にその時点でやはり債務整理をしない方が良かったことが判明したとしても、もはやブラックリストには載ってしまっていますし、またその時点で債務整理を辞めても一括請求の状態になっているため取返しが付かなくなります。
そのため、依頼前の相談・面談時において、正確な情報を伝えるように注意する必要があります。
Q:債務整理の相談先として「弁護士」「司法書士」の2つの選択肢があると思いますが、どちらの方が良いかご意見をお聞かせください
債務整理の相談先としては、弁護士の方が良いと思います。
もちろん、費用については一般的に司法書士の方が安い傾向にあり、依頼した場合も費用を少なくするという意味では司法書士の方が良い場合も多いです。
もっとも、弁護士は任意整理だけでなく、自己破産・個人再生についても代理人として対応することができますので、任意整理だけを無理に勧められることもなく、自己破産や個人再生も含めてどの手段を選ぶことがあなたにとって最適かという点から具体的に相談を行うことができます。
佐藤一清さんにインタビュー

監修者: 佐藤一清
武蔵行政書士事務所HP
2018年に武蔵行政書士事務所を設立。警察への各種届出・内容証明郵便の作成・相続・開業後のコンサルティング・顧問を中心とした業務と、法律に関するWEBマーケティングコンサルティングを行っている。2018年より「弁護士相談広場(https://www.bengohiroba.jp)」、2022年より「相続税理士マップ(https://askpro.co.jp/tax/souzoku/ )」の立ち上げ・企画をスタート。
佐藤一清のプロフィール情報
債務整理はどういった状況の人におすすめですか?
一般的に、借金の総額(住宅や車のローンは除く)が年収の30%を超えている人は債務整理を検討することがおすすめされています。
ただし、債務整理をするべきかどうかは、年収、借入先、家族構成、ライフスタイルなど、さまざまな要素によって変わってきますので、一概にいう事はできません。
そのため、「借金の返済がつらい」「借金を減らしたい」などと感じたら、まずは債務整理に詳しい弁護士や司法書士に相談してみることをおすすめします。
自己破産すると家族や配偶者に影響はありますか?
自己破産をした場合、自分名義の車や家を手放すこととなってしまいます。また現金もほとんど手元に残すこともできません。
自己破産をした場合であっても、保証人の返済義務は残りますので、家族や配偶者が保証人になっていると、家族に一括請求がくる可能性があります。
このように自己破産をすることで、家族の暮らしなどに大きな影響を与える可能性があります。家族や配偶者との相談、弁護士や司法書士との相談をしっかりとしたうえで決断を下すようにしましょう。
債務整理とは?

続いて、債務整理について4つの種類を詳しく解説していきます。
それぞれのメリットやデメリットに加えて、必要になる書類は何かまでご紹介しますので参考にしてみてください。
任意整理

任意整理とは利息や遅延損害金、適用金利の見直しをすることで債務者の負担を減らし、返済できるようにする債務整理の方法です。
さらに、過払い金があればその分のお金を取り戻すこともできるため、報酬支払いに充てることも可能となります。
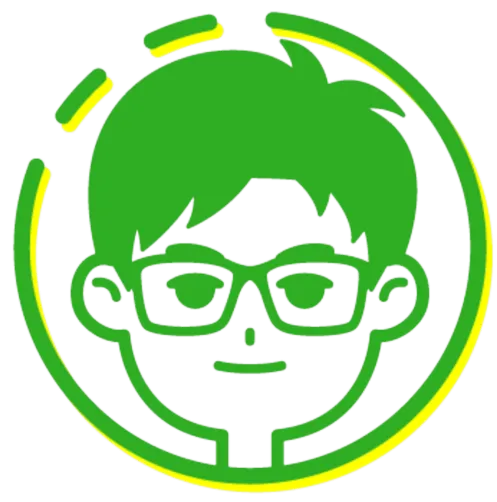
利息や遅延損害金の免除や減額になることは多いですが、元金の支払いは残ることがほとんどです。
任意整理は債務整理の中でも比較的利用しやすい方法で、毎年年間数百万人が任意整理を行っています。当サイトの独自アンケート調査でも、任意整理を行った人は数多くいることがわかりました。

| 任意整理 | 56.7% |
|---|---|
| 個人再生 | 28.7% |
| 自己破産 | 14.0% |
| 特定調停 | 0.7% |
アンケート調査:クラウドワークスにて実施
金融機関にて借金をしていて、返済額が生活資金を大きく圧迫しているなら、任意整理を検討してみることをおすすめします。
| 任意整理のメリット |
|
| 任意整理のデメリット |
|
・印鑑
・クレジットカード、ローンカード
・給与明細や源泉徴収票
・収入証明書類
・預貯金の通帳
・賃金時の契約書
・借入明細書や領収書
・送られてきた請求書
・貸金業者等から届いている督促状
・借入をしている業者一覧がわかる書類
・借入残高がわかる書類など
任意整理のメリットは、比較的短い期間で利息や遅延損害金などを減額することができるということです。
早ければ3ヶ月程度で和解締結まで完了するため、なるべく早く済ませたい方におすすめといえます。
また、任意整理は裁判所に行くことや官報に記載されることがないため、ほかの債務整理よりも周りの人にばれにくいという特徴があります。
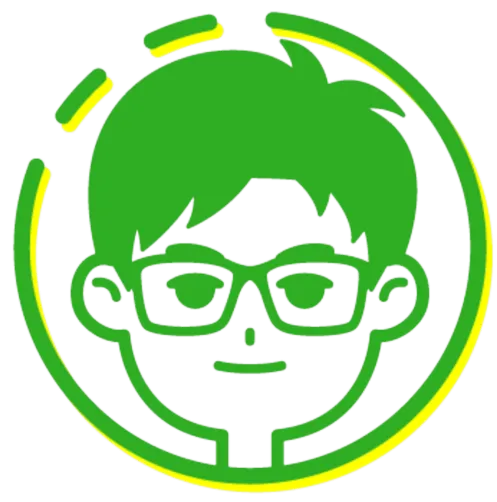
手続き中は督促もこないため、精神的に追い詰められることも少ないでしょう。
デメリットとしては、任意整理を行う条件として安定収入があるかどうかを求められることです。
条件を満たしていなかったり、返済する意思が認められない場合は任意整理することができないため注意しましょう。
また、任意整理の対象となるクレジットカードやローンカードはその後使えなくなりますので、覚えておきましょう。
>>任意整理による信用情報はいつ回復?登録期間についても解説
個人再生

個人再生は多額の借金を大幅に減額できる債務整理方法であり、利息や遅延損害金、元金も含めて減額することが可能です。
一般的に原則3年~5年の分割で返済を行う債務整理方法です。将来安定した収入が見込める人が対象となっており、場合によっては受け付けてくれないこともあります。
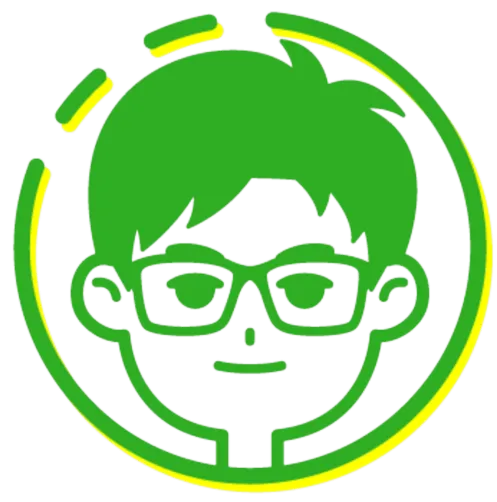
個人再生はよく自己破産と任意整理の中間といわれることが多いです。
自己破産のようにすべてを免責にすることは不可能ですが、債務を最大9割まで減額できます。よって任意整理よりも効果は期待できるでしょう。
その代わり、任意整理よりも条件は厳しくなる上にデメリットもあるため、債務整理の中でも選ばれることが少ない方法となります。
| 個人再生のメリット |
|
| 個人再生のデメリット |
|
・借入をしている業者一覧がわかる書類
・収入や財産がわかる書類
・家計全体わかる書類
・預貯金の通帳
・再生計画案
・返済計画表など
個人再生の大きなメリットは借金を大きく減額できることで、マイホームや車を手放すことなく借金を減額することができる場合があります。
さらに借金の理由を問われることがないため、ギャンブルなどで借金してしまった場合でも対応してくれます。
また、マイホームを残す場合は以下の条件を満たしていないと適応できないため注意してください。
- 個人再生をする本人が所有している
- 床面積2分の1以上が居住用であること
- 本人が現時点で住んでいること
- 住宅に住宅ローン以外の抵当権がついていないこと
- 対象となる住宅以外の不動産が住宅ローンの共同抵当となっている場合で、その不動産に後順位抵当権者がいないこと
そのため、個人再生をする際、マイホームや車といった財産を残したいのなら依頼する弁護士としっかり相談しましょう。
個人再生のデメリットは完済から5~10年の間ブラックリストに載ってしまうこと、すべての借金が対象であることです。
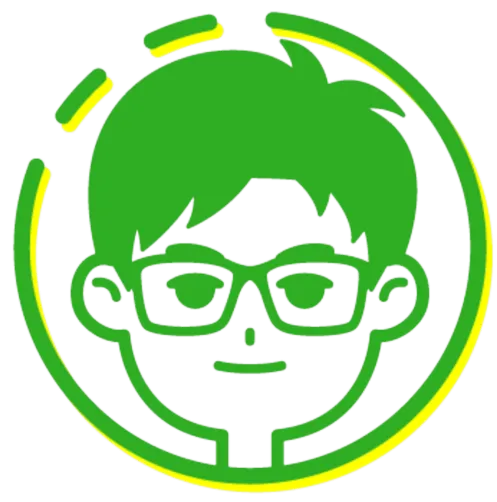
個人から借りたお金も対象となるため、家族や周りの人にばれやすいという特徴があります。
加えて、官報と呼ばれる国が発行する法律問題の機関紙に、自分の名前や住所などが掲載されてしまうため、調べればばれてしまうというリスクもあります。
自己破産とは異なり、個人再生後も残った返済を続けなければいけないため大変です。
また個人再生は、裁判所にて申し立てを行わなければいけないため、手続きに必要な書類は確実に提出する必要があります。
自己破産

自己破産とは収入や財産がなく、借金の返済ができないことを裁判所に認めてもらい、最低限の財産以外を取り上げられる代わりに借金を帳消しにすることができる債務整理方法です。
債務者は自己破産をすることで借金に追われることがなくなりますが、長期間社会的に不利な立ち位置を強いられてしまいます。
自己破産する人は毎年全国数万人いるため、極端に自己破産している人が少ないわけではないです。
また、同時廃止・管財事件・少額管財の3つの種類があり、それぞれ以下のような特徴があります。
- 同時廃止:財産がほとんどなく、免責不許可事由もない場合の方法
- 管財事件:債権者数が非常に多く、破産法上の問題点が多い場合の方法
- 少額管財:財産が多い場合や、免責不許可事由がある場合の方法
自分がどの方法に当てはまるかは、依頼する弁護士に相談することでわかります。
| 自己破産のメリット |
|
| 自己破産のデメリット |
|
・借入をしている業者一覧がわかる書類
・収入や財産がわかる書類
・住民票、戸籍謄本
・陳述書
・預貯金の通帳
・源泉徴収票、課税(非課税)証明書
・生活保護受給証明書など
自己破産を行うことで借金がすべてなくなるという最大のメリットがありますが、その分多くのデメリットもあります。
所有している財産がある場合は、必要最低限のもの以外すべて取り上げられてしまうため注意が必要です。

思い出の詰まったマイホームや車なども取り上げられてしまうため、精神的負荷も重くなります。
また、5~10年間はブラックリストに載り、官報にも掲載されてしまいます。
手続きを行っている間はさまざまな資格が制限されるため、期間中は資格を使った仕事ができなくなります。
自己破産を行う場合は、以下の条件に当てはまっていないと対応してもらえません。
- 裁判所に支払不能と認められる
- 過去7年以内に免責を受けたことがない
通常、弁護士に相談して裁判所に申し立てるところから始まっていくため、半年~1年程度自己破産までに期間を要することがあります。
また、過去7年以内に免責を受けていたとしても、債務者の事情によっては自己破産ができるため、迷わず弁護士に相談することをおすすめします。
自己破産に必要な書類の作成は弁護士事務所に相談すれば、基本的にすべて作成してくれるためおすすめです。
特定調停

特定調停とは債務者本人が簡易裁判所に申し立てを行い、債権者との仲介をしてもらいながら和解交渉を進めていく債務整理の方法です。
自分自身で裁判所に行き特定調停の申し立てを行わなければいけませんが、弁護士を活用した任意整理とは異なり費用が安く済みます。
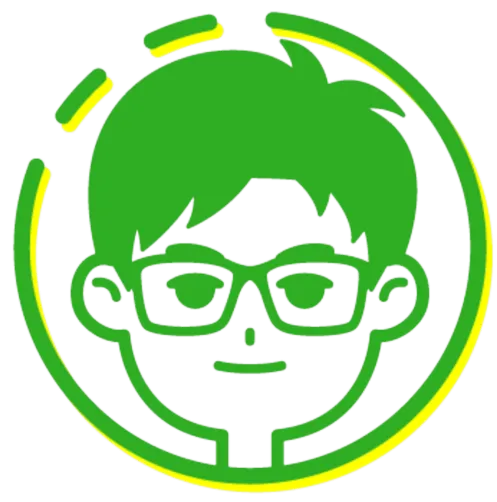
弁護士や司法書士を活用すれば楽に債務整理の手続きを進められるため、どちらを優先するかが重要です。
まずは特定調停を利用できる人はどんな人なのか見ていきましょう。
- 減額後3年程度で返済できる
- 安定した収入が見込める人
一般的な利用条件は上記となりますが、申し立てを行う簡易裁判所によっては条件や運用が異なる場合があります。
そのため、特定調停を行う場合は近くの簡易裁判所についてあらかじめ調べておくとよいでしょう。

| 特定調停のメリット |
|
| 特定調停のデメリット |
|
・調査表
・家計全体わかる書類
・源泉徴収票、課税(非課税)証明書
・賃貸借契約書や家賃の振込書のコピー
・光熱水道料の領収証や預金通帳等のコピー
・収入がわかる書類
・債権者の資格証明書
特定調停は自分一人で手続き等を完結できるのが特徴ですが、人によっては自分だけで手続きを終わらせられるかわからないと不安になる人もいるでしょう。
法律に詳しい知識を持っている方であれば、特定調停のほうが費用は安く抑えられるためおすすめです。
特定調停の受付票を送付することで債権者からの督促を止めることができるため、精神的な負担を減らすこともできます。
ただし、特定調停などの書類作成の手間があるためすぐには督促が止まるわけではないことも覚えておきましょう。

特定調停の受付票をはじめとした申し立てに必要な書類はすべて自分で用意しなくてはなりません。
簡易裁判所によっては求められる書類の種類は異なり、何度も訪れて手続きを行うことになるため、忙しい人は時間がかかりやすいです。
手間や時間がかかるのが嫌だという方は、費用をかけてでも弁護士・司法書士事務所に相談することをおすすめします。
特定調停を申し立てた場合に調停委員が債権者との交渉を行ってくれますが、債務整理の専門家ではないこともあります。
最悪の場合、特定調停を成立させることができないケースもあるため、よく考えて債務整理をしましょう。
特定調停をする場合は上記の書類が必要で、現在住んでいるアパートの賃貸借契約書や光熱費などのコピーを求められることもあります。
簡易裁判所や債務者の状況によって求められる書類が異なるため、電話等で確認することをおすすめします。
債務整理手続きの流れと費用
ここからは債務整理の手続きの流れと具体的な費用について解説していきます。任意整理・個人再生・自己破産すべての債務整理方法についてその流れをご紹介しますので参考にしてみてください。
任意整理の場合
まずは任意整理の手続きの流れについて詳しく見ていきましょう。
- 弁護士や司法書士と相談する
- 債権者と交渉する
- 返済計画を作成する
- 債務者が返済を開始する
- 債務整理の完了
弁護士や司法書士に任意整理の相談をして契約すると、対象となる賃金業者に受任通知を送付し、取引履歴などの開示請求などを行います。
受任通知を送った段階で債権者による直接の取り立てはストップします。
その後取引履歴をもとに「引き直し計算」と呼ばれる利息の再計算を行います。過払い金などはこの段階で見つけることが可能で、過払い金がある場合は返還請求をするのが通常の流れです。

交渉は基本的に依頼した弁護士や司法書士が債権者に代わってしてくれるため安心です。
債権者との交渉に基づき返済計画を立てていきます。返済計画には返済金額や返済計画などが含まれており、承認されたら計画通りに返済を進めていきます。
任意整理にかかる費用
任意整理にかかる費用は弁護士に依頼した場合3~10万円程度、司法書士に依頼した場合2万円~6万円と言われています。
司法書士の費用相場が低い理由は、対応できる借金額が140万円までに定められているからです。
個人再生の場合
個人再生の具体的な手続きの流れは以下の通りとなっています。
- 弁護士に相談する
- 再生計画案の作成
- 再生手続きの開始、申し立て
- 再生債務の支払い開始
- 再生債務の免除
- 再生手続きの終了
個人再生では借金の総額を調査して裁判所に個人再生の申し立てをするところから始まります。最終的に裁判所に再生計画案を認可されないと返済をスタートすることはできません。
個人再生にかかる費用は再生委員費用、弁護士に依頼するための費用に加えて債権の残った支払いがあります。具体的な費用について見ていきましょう。
| 再生委員費用 | 15万~25万円 |
|---|---|
| 弁護士に依頼する費用 | 40万円~70万円 |
| 債権の残った支払い | 再生計画案によって異なる |
上記のように個人再生には一定のお金が必要になりますが、自己破産と比べると負担はまだ少ないほうといえます。
弁護士に頼らず自分一人で個人再生を行うこともできますが、かなりの労力が必要となるでしょう。
自己破産の場合
自己破産には同時廃止事件と管財事件の2種類があり、それぞれ手続きの手順は異なります。また、自己破産も個人再生と同様に裁判所に支払うお金と弁護士に支払うお金があります。
| 自己破産するための費用 | 同時廃止事件 | 2万~3万円 |
|---|---|---|
| 管財事件 | 20万円~50万円 | |
| 弁護士に依頼する費用 | 40万円~70万円 | |
同時廃止事件と管財事件ではそれぞれ裁判所に支払う費用も異なります。管財事件として弁護士に依頼する場合は多額のお金が必要になることを覚えておきましょう。
同時廃止事件の場合
同時廃止事件の手続きの流れは以下の通りとなっています。
- 受任通知の送付
- 財産状況・家計収支の調査
- 自己破産申し立て
- 破産手続開始
- 免責許可決定
同時廃止事件の場合は、破産手続きを始めると同時に手続きが完了するため、スピード感があります。また、費用も弁護士費用に加えて裁判所へ支払う予納金などのため、2~3万円程度で済みます。
管財事件の場合
管財事件の手続きの流れは以下の通りです。
- 受任通知の送付
- 財産状況・家計収支の調査
- 自己破産申し立て
- 破産手続開始
- 管財人との面接
- 債権者集会
- 免責許可決定
管財事件は破産手続き開始後、破産管財人が選定されて自己破産者の財産調査や配当などを行います。裁判所へ支払う費用のほか破産管財人への報酬が必要となるため、20万円~50万円ほどを要します。
債務整理をするデメリット
初めて債務整理をする人は何かとわからないことが多く、不安になることも多いでしょう。ここでは、債務整理をするときの具体的な注意点について解説していきますので、参考にしてみてください。
- 信用情報にキズがつく
- 個人再生と自己破産は官報に載る
- 自己破産は財産を手放すことも
- クレジットカードやローンに申し込めない
信用情報にキズがつく
債務整理をするときの注意点は信用情報にキズがつくという点があります。
一般的に、債務整理を行うと信用情報機関にその旨が登録されるため、クレジットカードを作れなかったり、ローンを組めなかったりします。
信用情報に記録される期間は行った債務整理の内容に異なり、任意整理や個人再生は完済から5年程度、自己破産の場合だと最長10年の期間を要するので覚えておきましょう。
| 信用情報機関 | 登録される期間 |
| CIC(シー・アイ・シー) | 登録日から5年 |
| JICC(日本信用情報機構) | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
| KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 7年 |
個人再生と自己破産は官報に載る
2つ目の注意点は個人再生や自己破産を行った場合は官報に掲載されてしまうということ。
官報とは一般的に法律や政令、内閣官房のお知らせ、裁判所の判決などを掲載する政府機関の公報のことを指します。
官報には氏名と生年月日、自己破産申立日などが掲載されるため、家族を含める周りの人にバレる確率が上がります。個人再生の場合は個人情報は隠され匿名情報として官報に載ります。

官報に掲載されるからと言って必ずしも家族などにバレるわけではなく、載っているか調べないといけません。
自己破産は財産を手放すことも
自己破産を行うと、一定の財産を除き手放さなければいけない場合があります。財産を差し押さえられる理由は、自己破産者の債務返済に充てるためであり、債務の全額免除と引き換えに行われることです。
また、免責とされる財産の例は以下がありますが、どのような財産が取り上げられてしまうのか弁護士などに相談することをおすすめします。
- 生活必需品
- 一定額以下の預金・現金
- 解約返戻金額が一定額以下の生命保険
クレジットカードとローンに申し込めない
債務整理をすると信用情報にキズがつき、ブラックリストに載ります。ブラック状態になるとクレジットカードやローンへの新規申し込みができません。
なお、債務整理するとクレジットカードやローンを一生申し込めない・利用できないわけではありません。信用情報にキズがつくのは債務整理してから5年間で、それを過ぎれば申し込み可能です。
債務整理に関してよくある質問
債務整理におすすめの弁護士事務所は、サンク総合法律事務所となります。
サンク総合法律事務所は月に600件の債務整理相談を受けている実績を持っています。十分な実績を持っている事務所は経験やノウハウが豊富なため交渉が成立しやすいといえます。
また、何度でも無料相談ができたり分割払いに対応していたりと、利用しやすい費用設定がメリットです。
費用が安い弁護士・司法書士事務所でおすすめなのは、はたの法務事務所です。相談料や着手金無料で任意整理などを行えるという特徴があります。
弁護士・司法書士の選び方は、費用の安さや分割払い・後払いへの対応、夜間や土日でも対応などから比較するのがおすすめです。
自分が利用しやすいなと思える弁護士・司法書士事務所を選びましょう!
専門家に相談することで、迅速かつ適切なアドバイスや手続きを行ってくれます。債権者との交渉もしてくれるためスムーズに事が運びやすいです。
債務整理をする場合事故情報として信用情報機関に登録されます。任意整理や個人再生は完済から5年~10年程度、自己破産は最長10年登録されるので覚えておくとよいです。
使えなくなります。弁護士・司法書士事務所ではハサミで切った状態で渡されることもあるようなので確認を取るとよいです。
債務整理おすすめ弁護士・司法書士のまとめ
本記事では債務整理におすすめの弁護士・司法書士事務所や債務整理手続きの流れ、費用などをご紹介しました。債務整理を考えているのであれば、まずは弁護士や司法書士に相談するのが望ましいです。
また、債務整理について事前に理解を深めておくことが非常に重要となります。自身が該当すると思われる債務整理について理解を深めておけば、スムーズに手続きを終えられるでしょう。
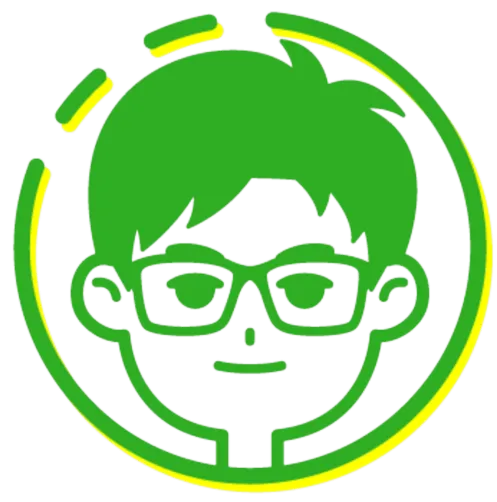
債務整理を検討している方は、本記事で紹介しているおすすめの弁護士・司法書士事務所を参考にしてみてください。
各弁護士・司法書士事務所の採点基準・ランキング根拠
モアマニ編集部では、当記事を制作するにあたって、おすすめの弁護士・司法書士事務所8社を比較しました。今回の検証にあたって比較した項目は以下のとおりです。
- 弁護士法人サンク総合法律事務所
- はたの法務事務所
- 東京ロータス法律事務所
- グリーン司法書士法人
- 弁護士法人・響
- ML司法書士事務所
- アース法律事務所
- ひばり(名村)法律事務所
- 弁護士法人ユア・エース
- ベリーベスト法律事務所
詳しい内容はこちらのランキング根拠ページをご覧ください。
- ①任意整理の着手金
- ②任意整理の基本報酬
- ③任意整理の減額報酬
- ④過払い請求の報酬
- ⑤相談料
比較項目①任意整理の着手金
●無料…5点
●有料…3点
弁護士法人 | 55,000円〜 | 3 |
|---|---|---|
はたの法務事務所 | 無料 | 5 |
東京ロータス法律事務所 | 1件22,000円 | 3 |
グリーン司法書士法人 | 無料 | 5 |
弁護士法人・響 | 55,000円〜 | 3 |
ML司法書士事務所 | 記載なし | |
アース法律事務所 | 1社あたり22,000円 | 3 |
ひばり(名村)法律事務所 | 1社あたり22,000円 | 3 |
弁護士法人ユア・エース | 1社あたり55,000円〜 | 3 |
ベリーベスト法律事務所 | 1社あたり22,000円 | 3 |
※記載されている金額はすべて税込です。
比較項目②任意整理の基本報酬
●1件22,000円未満…5点
●1件22,000円以上…3点
弁護士法人 | 債権者1件につき11,000円〜 | 3 |
|---|---|---|
はたの法務事務所 | 1社22,000円〜 | 3 |
東京ロータス法律事務所 | 1件22,000円 | 3 |
グリーン司法書士法人 | 1件21,780円 | 5 |
弁護士法人・響 | 11,000円〜(税込) | 3 |
ML司法書士事務所 | −(公式サイトに記載なし) | |
アース法律事務所 | 1社あたり22,000円 | 3 |
ひばり(名村)法律事務所 | 1社あたり22,000円 | 3 |
弁護士法人ユア・エース | 11,000円〜 | 3 |
ベリーベスト法律事務所 | 1社あたり22,000円 | 3 |
※記載されている金額はすべて税込です。
比較項目③任意整理の減額報酬
●11%以下…5点
●11%+1円以上…3点
弁護士法人 | 11% | 5 |
|---|---|---|
はたの法務事務所 | 11% | 5 |
東京ロータス法律事務所 | 11% | 5 |
グリーン司法書士法人 | 22% | 3 |
弁護士法人・響 | 11% | 5 |
ML司法書士事務所 | −(公式サイトに記載なし) | |
アース法律事務所 | 11% | 5 |
ひばり(名村)法律事務所 | 11% | 5 |
弁護士法人ユア・エース | 11% | 5 |
ベリーベスト法律事務所 | 22% | 3 |
※記載されている金額はすべて税込です。
比較項目④過払い請求の報酬
●取り戻した過払い金額の22%以下…5点
●取り戻した過払い金額の22%以下+別途何らかの報酬金…3点
弁護士法人 | 過払い金回収額の22% ※訴訟による場合は、過払い金回収額の27.5% | 5 |
|---|---|---|
はたの法務事務所 | 取り戻した過払い金額の22% 10万円以下の場合は14%(別途11,000円の計算費用をいただきます) | 5 |
東京ロータス法律事務所 | 回収額の22%(税込) | 5 |
グリーン司法書士法人 | 解決報酬金: 21,780円(税込) +回収額の22%(裁判ありの場合27.5%) | 3 |
弁護士法人・響 | 解決報酬金: 22,000円(税込) 過払い報酬金: 22% | 5 |
ML司法書士事務所 | −(公式サイトに記載なし) | |
アース法律事務所 | −(公式サイトに記載なし) | |
ひばり(名村)法律事務所 | 回収金の20%(税込22%) (但し、訴訟上の返還請求の場合は25%(税込27.5%))+実費 | 3 |
弁護士法人ユア・エース | 返還額の22%(訴訟の場合は27.5%)(税込) | 5 |
ベリーベスト法律事務所 | 解決報酬金: 22,000円(税込) 22%(裁判ありの場合27.5%) | 5 |
※記載されている金額はすべて税込です。
比較項目⑤相談料
●220,000円以下…5点
●220,001〜330,000円…4点
●330,001円以上…3点
弁護士法人 | 無料 | 5 |
|---|---|---|
はたの法務事務所 | 無料 | 5 |
東京ロータス法律事務所 | 無料 | 5 |
グリーン司法書士法人 | 無料 | 5 |
弁護士法人・響 | 無料 | 5 |
ML司法書士事務所 | 無料 | 5 |
アース法律事務所 | 無料 | 5 |
ひばり(名村)法律事務所 | 無料 | 5 |
弁護士法人ユア・エース | 無料 | 5 |
ベリーベスト法律事務所 | 無料 | 5 |
※記載されている金額はすべて税込です。
債務整理におすすめの弁護士・司法書士事務所の総合点数
弁護士法人 | 21 | 4.2 |
|---|---|---|
はたの法務事務所 | 23 | 4.6 |
東京ロータス法律事務所 | 21 | 4.2 |
グリーン司法書士法人 | 21 | 4.2 |
弁護士法人・響 | 21 | 4.2 |
ML司法書士事務所 | 5 | 5 |
アース法律事務所 | 16 | 4 |
ひばり(名村)法律事務所 | 19 | 3.8 |
弁護士法人ユア・エース | 21 | 4.2 |
ベリーベスト法律事務所 | 19 | 3.8 |
※公式サイトに情報の記載がない場合は、その項目は含めずに採点しています。

債務整理担当ライター・編集者Rさん
借金が膨れ上がってしまうことで心の余裕がなくなってしまうのは、珍しいことではありません。そんな借金で困っている方向けに、誰にでも分かりやすく情報をまとめることを意識して、日々記事の執筆・編集を行っています。
債務整理の記事はこちら

・本記事の内容は、本記事内で紹介されている商品・サービス等を提供する企業等の意見を代表するものではありません。
・本記事の内容は、本記事内で紹介されている商品・サービス等の仕様等について何らかの保証をするものではありません。本記事で紹介しております商品・サービスの詳細につきましては、商品・サービスを提供している企業等へご確認くださいますようお願い申し上げます。
・本記事の内容は作成日または更新日現在のものです。本記事の作成日または更新日以後に、本記事で紹介している商品・サービスの内容が変更されている場合がございます。
・本記事内で紹介されている意見は個人的なものであり、記事の作成者その他の企業等の意見を代表するものではありません。
・本記事内で紹介されている意見は、意見を提供された方の使用当時のものであり、その内容および商品・サービスの仕様等についていかなる保証をするものでもありません。














